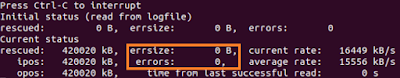UBUNTUなどをインストールした際にできる GRUB を削除する方法

主に Ubuntu などの Linux OS をインストールした際に作成される GRUB (主に Linux で使用される ブートローダー) 基本的には、ブート位置の修正で直ります。 Windowsインストールディスクからコマンドプロンプトを実行 bcdboot c:\Windows で起動すると思います。 ※上記でダメな場合は、システム領域(EFI\Microsoft\boot\BCDのある場所) にドライブレターを割り当ててから(例:X:\) bcdboot c:\Windows /l ja-JP /s X: /f ALL を実行する必要があるかもしれません ー しかし BCD には Ubuntuの情報や システム領域にファイルが残ったままになっています。 特に Windows を起動する上では、問題はありませんが 起動時にブート選択時に Ubuntu と表示されたままになります。 それらも削除する方法 1.Ubuntu の identifier を調べる コマンドプロンプト(管理者)を起動 bcdedit /enum firmware を実行し、ファームウェアアプリケーションにある description が Ubuntu のものを探す。 2.Ubuntu の identifier {固有の英数字}をコピー { }を含み 選択しコピーする 3.削除するコマンドを実行する bcdedit /delete {********-****-****-****-************} {**~**}は上記でコピーしたもの これでブート項目から Ubuntu を削除できました。 ー GRUB本体を削除する方法 1.システム領域にドライブレターを割り当てる 同じく、コマンドプロンプト(管理者)を起動 ※以下はディスク0番、システム領域がボリューム1番でXドライブとしての例 lis dis sel dis 0 lis vol 1 assign letter=x exit 2.GRUBが格納されているフォルダを削除する (※...